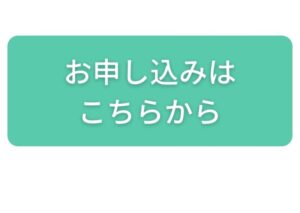11/29(土) 干し柿作りボランティア2025の参加者を募集します!(こすげ村人ポイントカード会員様限定)

小菅村では、渋柿は11〜12月ごろに収穫期を迎えます。
しかし、小菅村では高齢化が進み、高齢者では渋柿の収穫ができずに放置されてしまっている状況があります。
また、小菅村では、山で暮らす野生生物が里まで下りてきて畑を荒らす「獣害」が深刻化しています。
11〜12月はちょうど山にも食べ物がなくなる時期で、渋柿は獣たちの格好の食べ物です。
そんな獣害被害を少しでも減らそうと、毎年渋柿を収穫し干し柿作りに取り組んでいる村民がいます。
そこで、11月29日(土)に干し柿作りのボランティアを募集します(先着15名)!
(こすげ村人ポイントカードについてはこちらから)
小菅村の渋柿を使い、獣害対策にもつながる干し柿作りをお手伝いいただけませんか?
当日は、事前に収穫した渋柿の皮をむくところから吊るすまでの作業を行います。
 ①収穫した渋柿は包丁・ピーラーを使って皮をむきます。 |  ②大きな鍋で、湯通し。 |
 ④近くのカーポートに吊るして1か月後の完成を待ちます。 |
当日一緒に干し柿作りの作業をするのは、毎年小菅村で干し柿を作り、獣害対策を本業とする青栁博樹さん。

当日干し柿にする渋柿は青栁さんが収穫するものです。木に登り、竹の竿を使って1つ1つ収穫をします。
\2022年の様子はこちらから/
当日のスケジュールです。
| 10:10 | 集合 ●車でお越しの方:小菅村中央公民館3Fにお越しください。 ●バスでお越しの方:10:00に小菅の湯前に集合してください。そこから小菅村中央公民館3Fまで送迎車にて移動します。 ※アクセスの詳細は、”よくあるご質問”に掲載しています。 |
| 10:20 | ガイダンス・作業開始 小菅村中央公民館3Fにて、干し柿作りを地元の方に教えてもらいながら一緒に作業しましょう! 作業内容: ・皮をピーラーでむく ・湯どおし ・ひもを付ける ・干す ※皮むきから始め、状況によってそれ以外の作業をお手伝いいただきます。 |
休憩 大変な作業ですが、休憩を挟みつつがんばりましょう! | |
| 13:00頃 | 作業終了予定、解散 ※作業状況や柿の収穫量によって終了時間は前後する可能性があります。 ※バスでお越しの方は、小菅の湯へ送迎いたします。 |
昼食後 ~ 15:30頃 | (希望者のみ)午後も作業を行いますので、ぜひご協力ください! 午前中に作業が終わらなかった場合は、午後も干し柿作りを続けて行います。 午後もお手伝いいただける方は、ぜひご協力ください。 各自で昼食をとった後、午前中と同じ場所でお手伝いいただきます。
※昼食はご持参、古民家cafeムッカへ、また徒歩圏内にある”ひろせ商店”でも購入いただけます(会場にはキッチンがあります。電子レンジ・お湯などご利用いただけます)。お車でお越しの方は、その他村内の食事処もご利用いただけます。 |
| 日程 | 2025年11月29日(土)雨天決行 ※荒天や道路通行止め等の状況の場合は、実施を中止します。 ※例年 柿の生育状況を考慮して予備日を設けていましたが、今年は予備日はありません。 |
| 会場 | 小菅村中央公民館3F (住所:山梨県北都留郡小菅村4581番地) |
| 参加費 | 一人200円(保険料として) |
| 参加条件 | 小学生以上(小学生のお子様は保護者要同伴) |
| 代金に含まれるもの | 保険料 |
| 代金に含まれないもの | 会場までの交通費、昼食代 |
| 定員 | 15人 |
| 主催・運営 | ●企画主体 株式会社 源 こすげ村人ポイントカード事務局 山梨県北都留郡小菅村3445番地 問い合わせ先:070-4425-4378(10:00~17:00 土日祝除く) |
必ずお持ちください。
| # | 服装・持ち物 | 備考 |
| 1 | 作業用手袋 | ニトリル手袋、ポリ手袋などの手袋をお持ちください。(柿渋での汚れ防止及び衛生対策として) ピーラーで破れた時のために予備があると安心です。 |
| 2 | エプロン | 作業中に着用。柿渋で汚れます。 |
| 3 | 三角巾や手ぬぐいなど | 髪の毛が下に落ちないように頭を覆うものです。 |
| 4 | マスク | 衛生対策として(息苦しくなった場合は、取ってもらっても構いません) |
| 5 | 防寒着 | 寒い屋外への移動があります。室内は暖房をつけますが、暖かい服装でお過ごしください。 |
| 6 | 汚れても良い上下 | エプロンだけでも良いですが、汚れても良い上下で作業いただくと安心です。 |
| 7 | 参加費 | 200円(当日、受付にて現金でお支払いください。) ※損保ジャパンの「レクリエーション補償プラン」に加入します。 |
ご家庭にあれば・必要に応じ、以下もお願いします。
| # | 服装・持ち物 | 備考 |
| 1 | ピーラー | 皮むきに使います。使い慣れたものがあればお持ちください。 会場にも準備がありますが、切れにくいかもしれません。 |
| 2 | ステンレスの包丁 | ヘタの部分のカットに包丁を使います。使い慣れたものがあればお持ちください。
※刃体の長さが6cmをこえる刃物の持ち運びは銃刀法違反の対象となるので、新聞紙などでくるみ、すぐに使用できない状態でお持ちください。 ※鋼(鉄製)の包丁は渋柿のタンニンと反応して、柿が黒くなってしまいますので、必ずステンレス製のものをお願いします。 |
| 3 | 休憩時の飲み物やお菓子、昼食 | 大変な作業なので、途中で休憩を挟みながら行います。 午前中に作業が終わらなかった場合は、午後も干し柿作りを行う予定です。会場にはキッチンがあり、電子レンジ・電気ポットなどご利用いただけます。 |
| 4 | 折りたたみ椅子や座布団 | 皮むきは、床での作業になります。 冷えを防ぐことができる銀マットは用意しますが、長時間座りっぱなしが大変な方は、折りたたみ椅子や座布団などがあると便利です。 |
申し込みは以下のお申し込みフォームにご記入ください。
※こすげ村人ポイントカード会員様限定で、募集定員は15名、先着順です。申込者様以外の同行者様は会員様でなくても構いません。
(こすげ村人ポイントカードについて、お申込みはこちらから)
※お申込締め切り:2025年11月14日(金)16時まで
Q: 会場まで車で行く場合の注意事項やルートを教えてください。
Q: 小菅村までバスで行く場合のアクセスについて教えてください。
Q:ボランティアに申し込みをしたいのですが、ポイントカード会員ではありません。どうしたらよいですか?
Q:当日の天候や体調により、欠席をしたい場合はどうしたらよいですか?
Q:柿を採るところからお手伝いしたいです。
Q: 過去のボランティアの様子が知りたいです。