バーベキューに欠かせない木炭が小菅村で作られていた!「炭焼」の歴史
2022/01/07 ライター:atsumi

村の面積の約95%が森林に囲まれた小菅村。
そんな小菅村では古くから林業が営まれ、木材は主に建築用材や木炭として活用されました。
現代ではバーベキューなどで使うことの多い木炭ですが、昔は料理や暖房のための燃料として使われるなど、より暮らしに根付いたものであったようです。
小菅村でも、暮らしに必要な木炭を自分たちで作っていた歴史があります。
木炭を作ることは「炭焼(すみやき)」と呼ばれます。
今回は、小菅村の炭焼について調べたり話を聞いたりしながら、実際に自家用に炭焼を行う村民の方にその様子を見せていただきました。
木炭を作るために行われる「炭焼」とは?

炭焼(すみやき)とは、木炭を作ることをいいます。
木炭は、山から切った木や竹を、石や粘土から作られる炭焼窯に入れ、蒸し焼きにすることで作られます。
そのまま木を燃やすと、燃え尽きて灰になってしまいます。
しかし炭焼窯の中で空気を遮断した状態で木を焼くことで、炭化し木炭ができあがります。

木炭は燃やしても煙や炎がほとんど出ないので、昔は家の中での料理や暖房にも使われていたそうです。

小菅村の特産品である川魚のヤマメの塩焼きも、木炭でじっくり焼かれることで美味しく仕上がります。
木炭には黒炭と白炭の2種類がある
木炭には、黒炭(くろずみ)と白炭(しろずみ)の2種類があります。
小菅村では白炭が多く作られていたそうです。

左は表面が黒いまま仕上がる黒炭、右は表面が白っぽく見える白炭です。
木が黒炭か白炭になるかは、炭焼の工程によって決まります。
黒炭は炭焼窯で蒸し焼きにした後、火が消えて自然に冷却されるまで、木炭を窯の中に入れたままにしておきます。
一方、白炭は炭焼窯で蒸し焼きにした後、木が高熱で赤くなっている状態で炭焼窯から取り出し、土と灰を混ぜたものをかけて、火を消します。
土と灰をかけることで、木炭の表面が白っぽく見えることが「白炭」と呼ばれる理由だそうです。

ホームセンターなどで売られているのは、黒炭が一般的です。
黒炭は、火がつきやすいが、燃える時間が短い。
白炭は、黒炭より火がつくまでに時間はかかるが、その分火の持ちがよいという特徴があります。
小菅村での炭焼の歴史
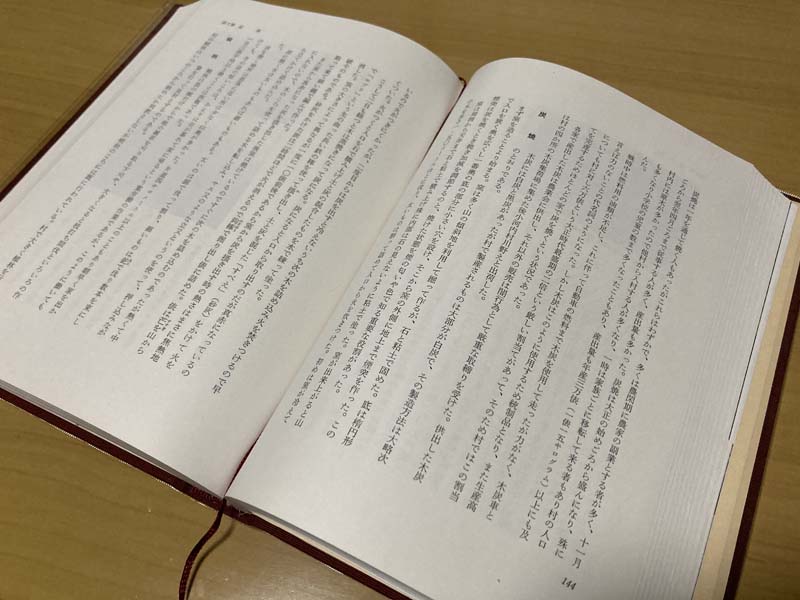
小菅村の歴史や地理、文化や暮らしについてまとめられた「小菅村郷土小誌」に炭焼についての記載がありました。
いつ頃から小菅村で炭焼が行われていたかは定かでありませんが、
現在のように炭焼窯を作って行われる炭焼については、明治時代に旅人が来て始めたと伝えられています。
特に大正の初めごろ(約100年前)から盛んになり、村外から家族で移住して炭焼を行う人もいたとのことです。

現在では、炭焼を生業とする人はいませんが、村内の数か所に炭焼窯が残っています。
実際に村民の方に話を聞いてみました。
今回はそんな炭焼について、長作地区に住む村民の守重敏夫(もりしげとしお)さんにお話を伺いました。

敏夫さんは自衛隊や小菅村役場の職員として働いた後、小菅村内で林業のお仕事をしていたそうです。
ー昔は敏夫さんの家でも炭焼をしていたのですか?
父親が農業と炭焼を行っていました。
小菅村では農閑期に炭焼を副業とする農家が多かったため、炭焼は11月から4月頃に行われることが多かったです。
春から秋にかけては、大麦や小麦、こんにゃく、じゃがいも、トウモロコシ、ネギ、キュウリ、インゲン、そば、大豆など様々な作物を作っていました。
しかし冬は畑で育つ作物も限られるため、炭焼で生計を立てていたのです。
馬に炭を乗せて、隣町まで売りに出ていました。
そして木炭を売り、その対価として酒などを買う物々交換をして、村に帰ってきたのです。
ー敏夫さんの住む地区ではいつ頃まで炭焼をしていたのですか?
同じ地区に住む方(現在84歳)のお父さんが炭焼を商売でやっていた約20年前を最後に、この地区でも炭焼をする人はいなくなりました。
炭焼の様子を見せていただきました。
今回は敏夫さんに黒炭を焼く様子を見せていただきました。

敏夫さんの炭焼窯は、1~2日かけて趣味で畑の一角に作ったものです。
アーチ状になっている釜の上部はドラム缶を切り抜いて土台にしています。
昔の炭焼窯は石や粘土だけで作られたそうですが、頻繁に炭焼をしないと湿気で天井が落ちてきてしまうため、敏夫さんの窯はドラム缶を使ったそうです。

炭焼窯の隣にはかまどもあり、春には山から採ってきたタケノコ、夏には畑のじゃがいもを茹でたりと小菅村の自然に寄り添った暮らしをしています。
まずは1日目の夕方、乾いた木を炭焼窯へ入れる作業をしました。
炭焼では、切ったばかりの木を使うと水が出て上手く蒸し焼きにならないので、乾かした木を使います。

炭焼窯の近くに、敏夫さんが山から切り出してきた木が積まれていました。
昔はそれぞれが所有している山に炭焼窯があり、山で木を切り炭焼をしていたそうです。
山から木を運び出すのは大変な作業なので、山に炭焼窯を作り、切った木を窯の近くで乾かし炭焼をしました。
今回の炭焼では乾いたナラの木を使いました。
ナラの木から作られる木炭は、火力が強く長く燃えます。
そのため、木炭を村外に売りに行っていた頃も、ナラの木炭は高く売れたそうです。

入口が小さいので細長い木の棒を使って、ナラの木を炭焼窯の奥に詰めていきます。

炭焼窯の手前には燃えやすい枯れた木(今回はクワの木)を立てかけます。炭焼窯の手前にある木は焚き付けのために使われ、炭にはなりません。
ここで1日目の作業は終了です。
今回は日の出ている時間で主な作業ができるよう逆算し、火をつけるのは2日目の朝となりました。

2日目の朝、手前の木に火をつけます。

奥のナラの木へ燃え広がる程度まで火が大きくなるのを待ちます。
火をつけてから2時間程度、入口を開けたまま火の様子を見守りました。

煙突に開けたから穴から、だんだんと木酢液(もくさくえき)が垂れてきました。
敏夫さんの長年の勘で、火が十分な大きさになったと判断したら、入口をしっかりと塞ぎ、蒸し焼きの状態にします。
空気が炭焼窯の中に入らないようにすることで、中の木が灰ではなく木炭になるのです。

入口にブロックを置き、さらにすき間を土でふさぎます。
炭焼窯の中は1000℃近くまで熱くなるそうです。

煙突から出る煙が強烈で、昔は山で行う炭焼きの煙が離れた家まで届いて、煙たくなることが度々あったそうです。

煙が青っぽくなり、やがて煙が出なくなると、中の木が全て木炭になった合図です。
今回はおおよそ火をつけてから12時間ほどで煙が出なくなりました。
4日目、いよいよ木炭が出来上がりました!

火が消え、中の炭が自然冷却された2日後、いよいよ入口を開けて、炭焼窯から木炭を取り出します。

自然冷却されるのにおよそ1~2日かかります。今回は2日後に取り出しました。

今回は黒炭ということで、自然冷却された状態で取り出しました。
白炭の場合は木炭ができたら高温の状態で取り出し、灰と土を混ぜたものをかける大変な作業があるそうです。

バーベキューが何度かできそうな量の木炭が出来上がりました。
出来上がった木炭で、親戚や知り合いが小菅村へ遊びに来た際にバーベキューを振舞うこともあるそうですよ。
自然と共にある小菅村の暮らし
小菅村で炭焼をしていたことは知っていましたが、今回初めて当時のお話を聞き、炭焼の様子を見せていただきました。
10年前くらいには、自家用に冬に炭焼をする煙を見たり、こたつを炭で暖めたりという家もありましたが、今では数少なくなっているそうです。
当時の暮らしを想像しながら、自分たちの暮らしは自然に生かされているのだなあと改めて感じる機会となりました。
炭焼をしていた時代から暮らし方は変わってきていますが、小菅村には自然に寄り添った暮らしがあります。
ぜひ小菅村でそんな里山の暮らしを感じてみてください。

atsumi
2018年6月に千葉県から小菅村に移住。村の皆様からくらしの知恵を学びつつ、村の魅力を発信していくべく働いています!趣味は美味しいものを食べること・飲むこと。料理はまだまだヒヨコレベルです…。






